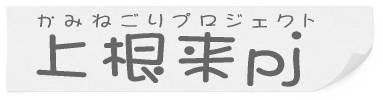上根来はこんなとこ
■集落の概要

小浜市上根来は、小浜市街地から車で 30 分、遠敷側上流の標高 300m付近にある山里で、かつては炭焼きや農業等を営み人口 300 人を数えましたが、現在は住民実質ゼロ人となっています。
しかし上根来に行ってみると、そこは廃村の風情ではありません。多くの家はきちんと手入れされて、草刈りや溝掃除もされていて、まるでまだ人々が住んでいるよう。

それもそのはず、上根来には元住民の会である「百里会」があり、今でも年に数回の清掃作業をしています。元住民の皆さんも冬には雪囲いをしたり雪下ろしをしたりして家屋を維持し、お盆にはお寺が満員になるほどの人たちが集まります。
上根来は人口ゼロ人なのに、地域コミュニティが残っている不思議な集落なのです。
■鯖街道お休み処・助太郎

平成28年10月、上根来集落入り口の民家を改装して、鯖街道お休み所「助太郎」がオープンしました。どなたでもお気軽にお越しください。
開館日:4月から11月の毎週土・日曜日
開館時間:10時~16時
※ご連絡をいただければ臨時開館します。
※トイレは24時間ご自由にお使いいただけます。水洗シャワートイレです。

助太郎は明治15年ごろの建造と思われます。
特に「網代組み」と言われる梁を互い違いに組んだ天井組みは見事で、重機も機械もない時代にこのような美しくも頑丈な建築をしていたことに驚くばかりです。
囲炉裏やムロ(貯蔵庫)も残っており、里山の暮らしを肌で感じることができます。

室内には鯖街道や上根来集落の展示もあり、小浜から京の都へ海産物を運ぶ最短ルートでもあった鯖街道「針畑越え」と、その中継地点であった上根来集落の歴史を学ぶことができます。
また鯖街道や遠敷峠周辺の山々を歩く人たちのために、様々なマップ等も置いてありますので、ご自由にお持ちください。

これは平成29年5月の「鯖街道ウォーク」の時の休憩シーン。山歩きやバードウォッチング、学校の野外活動など、様々なイベントや個人活動でお使いいただけます。
使用料等は無料です。
このHPの「お問い合わせ」のページからお気軽にお問い合わせください。
■ゲストハウス・与左衛門

助太郎のすぐ裏手に、別の民家を借用したゲストハウス「与左衛門」があります。
上根来プロジェクトの活動拠点であるとともに、希望者はお泊まりいただくこともできます。また、希望者には実費をいただいて食料調達・貸し布団調達をしています。
ただしご宿泊の場合は、運営協力金としてお一人あたり1,000円を頂戴しています。
ご利用をご希望の方はこのHPの「お問い合わせ」のページからお問い合わせください。

居間は真ん中に囲炉裏のある8畳間です。
玄関口には昔なつかしい黒電話があり、きちんと使えるようにしてあります。通話料は常識の範囲内で無料ですが、遠距離電話・長電話のときは自己申告でいくらかいただいています。
なお、auとソフトバンク系は携帯電話も使えます。

トイレは水洗トイレですのでご安心ください。(ただしシャワートイレではありません)
またお風呂も温水器でお湯を沸かし、シャワーも使えます。台所ももちろんあり、ガスはありませんが電熱器・電子レンジ・炊飯器があり、調理器具や食器類もあります。また洗濯機・乾燥機・冷蔵庫も自由に使えます。

数人分の食器類や紙皿紙コップ割り箸類、蚊取り線香や殺虫剤、ゴミ袋類、その他生活に必要なものはひととおりそろえてあり、これらはご自由にお使いいただけます。
懐中電灯やヘッドランプ、BBQコンロ、小型テント、投光器、ハンモック、こたつなどもお使いいただけます。

玄関前でバーベキュー。
ここを拠点にしてトレッキングにいったり薪割りや昆虫採集をしたり、家族で「夏休みの探検」をしてみてはどうでしょう。車で15分ほど走れば「お水送り」の鵜の瀬やとびきりの歴史を持つ寺社、箸研ぎ体験施設などもあります。
■茅葺き民家
<この文章は、浦野さんのホームページからお借りしています>

全17戸の山村、上根来。民家のおよそ半数は茅葺き屋根を乗せています。いまは雨漏りを防ぐため、すべてトタンでおおわれていますが…。
それはさておき、上根来の茅葺き民家の特徴をざーっとあげてみましょう。
・平入り、入母屋づくり、平屋建て
・間口は8間(梁間は4間)
・壁は板張りで、土壁は使わない
・開口部が少ない
・サッシをつけている家もあるが、オリジナルは四面ともほぼ壁だったと思われる
・縁側がなく、雪囲いをもつ
・高さ20~30cmの石垣(土台)をつくり、その上に家を建てているものもある

どの家も、どちらかといえば小ぶり。そして大きな屋根と、いかにも「雪国だな~」って思わせるつくりが印象的です。
とくに開口部が少なく、壁が板張りであることなんか、冬の過酷さが身にしみてくるようですね! (土壁は、壁の中の水分が凍るとひび割れてしまうため、寒冷地には適さないのです)。そしてほとんどの家が、トタンの雪囲いを備えています。

石垣(土台)をもつ家も目立ちますね。上根来は山間部に開けた集落のため、土地をならすための措置だと思います。
■稲木をもつ家
<この文章は、浦野さんのホームページからお借りしています>

上根来の民家の見どころは、家のまわりにもあります。そのひとつ、稲木(いなき)もまた、素朴な風情をかもし出しています。
これは細い木の枝を縦横に組み上げたもので、収穫した葉物野菜や豆なんかを干すのに使ったのだそうです。特徴は、家の近くにあるケヤキの木を支柱としてつくられていること。村で畑作が行われなくなって久しいのですが、いまでも村に2カ所残っています!! 稲木は本来、作物を収穫する冬のあいだだけつくられるのだとか。季節外れに取り残された姿は、どこかさびしげでもありました。
■上根来山の家(旧上根来小学校)

上根来集落から少し降りたところに、標高250mのあたりに上根来小学校跡がありました。
上根来集落は標高300m、下流の中の畑集落は標高200mのあたりにありますから、小学校はちょうどその中間にあるわけですが、当時の子どもたちは自分の足で毎日50mも上り下りしていたんですね。

昭和の終わり頃に閉校になり、それから山の家として体験宿泊などに使われてきましたが、老朽化が激しく、電気も切られ、ひっそりと最期の時を待っていました。
木造1階建て、講堂・教室2部屋・理科室・職員室・事務室がありました。
これは講堂。板張りで、体育館というような広さではありません。

理科室?準備室?人体模型やホルマリン標本もあって、肝試しに持ってこいかな?
昭和のころの子どもたちの写真も飾ってありました。
最後の卒業生も今では40代。
この部屋にいると、上根来集落に子どもたちがいた昭和の時間が、もう進むことなく残っているのを感じます。

講堂に掲示されていた、子どもがお店屋さんのことを書いた絵です。
私たちにはわからない名前の店が多いのですが、きっと下流の遠敷にある(あった)店なんでしょうね。
スポンジを「すっぽんじ」と書いてあったのが何ともかわいらしく、爆笑してしまいました。

講堂の黒板には、ここを訪れた人たちが書き残したメッセージが。
卒業生のものもあって、感慨深く見入ってしまいました。
この小学校は最盛期には30人近い児童がいたようです。
教室が2つですから、最初から複々式授業だったのですね。

講堂だけでなく、廊下や教室のあちこちが雨漏りします。講堂の天井にはシミがいっぱい。
棟瓦がズレてしまっており、なんとかしたいとブルーシートをかけたりもしましたが、そんな小手先ではやはりどうにもならないところまで来ていました。
この建物は少しずつ確実に最期の時に向かっているのだなと感じました。

晩秋の上根来小学校。
校庭には紅葉が植えられており、秋には見事に紅葉します。
静かに佇む校舎跡と色鮮やかな紅葉、まばらに色づいた山々が素晴らしいですね。

ところが平成30年度になって、腐朽が進む校舎が危険になってきたので、取り壊されることが決まりました。
5月、TV収録の機会に集落元住民の皆さんで記念撮影。

そして10月、ついに取り壊し工事が始まりました。
写真は12月の更地に戻った校地です。
本当にさみしい風景ですが、いつかこの広い土地を活用できないものかなとも思っています。
■神社

集落からちょっと上がったところに神社があります。

境内には太い杉が何本もあって、荘厳な雰囲気です。
無住の集落の神社とは思えないほどきれいで、集落の皆さんが今でもきちんと神社を守っていらっしゃることがわかって感動します。

本殿に象の彫り物を発見!
普通ここは雲か何かの模様を彫ってあるのですが、明らかに象です。
小浜は日本で最初に象が来たところ。その象は、何本もある鯖街道のどれかを通って京の都に行ったとか。そしてこの神社の前の道は、かつての鯖街道のひとつでした。
…実に興味深いですね。
■みのくぼの池

畜産団地跡の裏山を「宗山」といいます。標高600mほどの山で、中腹まで間伐作業道ができています。
この山頂から尾根沿いに少し行くと窪地があり、ここに池があります。
初夏にはモリアオガエルがたくさん卵を産みます。こんな山の上にモリアオガエルが繁殖しているのですから、この池は涸れることがないのでしょう。
不思議な池ですね。
■ねごりの子守歌

上根来集落から7kmほど下ったところに下根来集落があり、ここに旧・下根来小学校があります。平成20年に遠敷小学校に併合され、廃校になりました。
校庭の一角に「ねごりの子守歌」の碑があります。

下根来でずっと歌い継がれてきた子守歌。
KAZ先生が発掘されて編曲し、下根来の子どもたちが演奏していました。

ギターコードが書いてあるところがKAZ先生らしいですね。